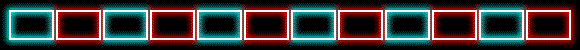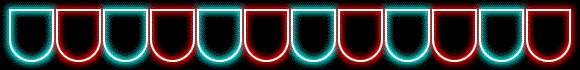
神様との出会い
1.藁の社
我が家には私が子供の頃から家の片隅に小さな藁で出来ている祠がありました。 この祠は家の守り神を祭っているもので、普通は家の戌亥の方角といわれる西北の隅に祭られている五穀繁盛を意味する稲荷の神の社なのです。 社と言っても今みたいな立派なものではなく、藁で小さな屋根が作ってあり、中に幣束がたった一本入っていただけのもので、特に目立つ社でもなく粗末なものでした。 そんな社を、子供の頃から悲しい事やつらい事があった時など、気がつくといつも前に座り、じっと手を合わせてお願いしていた記憶があります。遊びに出て行った先で友達と喧嘩してしまったり、家の中では姉弟げんかをしたり、時には親父に叱られたりと落ち込んでいた時など、困った時にはいつもこの社の前で自然と手を合わせていたものです。 信じるという事は恐ろしいもので、子供ながらにその藁の社の前に座り、中に神様がいると信じ、一心に手を合わせて語りかけていた記憶が何度もあります。 そんな時にはいつしか心が落ち着き元気を取り戻していたものでした。 |
戻る
| トップ |